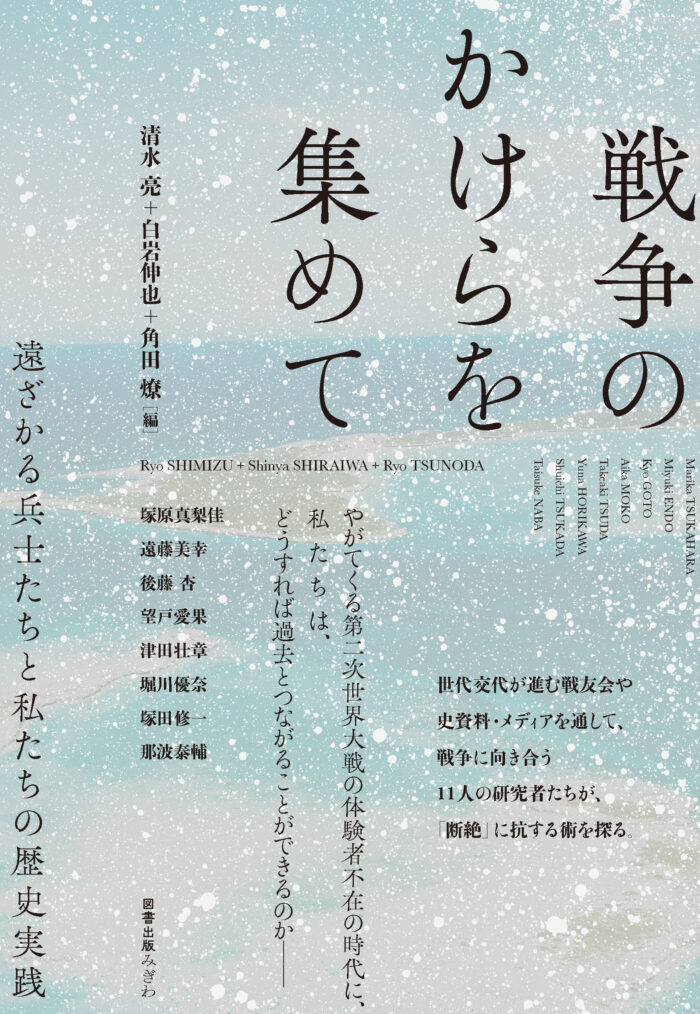
戦争のかけらを集めて
遠ざかる兵士たちと私たちの歴史実践
清水亮・白岩伸也・角田燎 編
体裁:A5判・並製・カバー装・320頁
価格:本体3,200円+税
刊行:2024年6月刊行予定
ISBN978-4-911029-09-1 C0020
やがてくる第二次世界大戦の体験者不在の時代に、私たちは、どうすれば過去とつながることができるのか――
元兵士から非体験者への世代交代が進む戦友会や、戦争を伝える史資料・メディアに向き合ってきた11人が、研究という回路を通して、忘却に抗する可能性を示す。
偶然出会った個人の生と死、戦後の片隅にいた集団の断片的な物語などを拾い集め、埋もれた歴史経験のリアリティを描きだす。これからの継承のかたちを構想し、過去の戦争が「歴史」になる時代に何ができるのかを考える。新しい研究者たちによる挑戦の一冊!
「歴史は、こちらが一方的に掘り進める化石ではない。私たちが歴史に働きかけるとき、歴史も私たちに働きかけてくる。(略)歴史実践は相互行為だ」(本書「プロローグ」より)
【目次】
プロローグ あの戦争は「歴史」になったとしても 清水亮
第1部 非体験者による存続の行方
戦後七〇年の軍艦金剛会 「追憶」のためのノート 塚原真梨佳
不戦兵士の会 元兵士と市民による不戦運動の軌跡と次世代への継承 遠藤美幸
なぜ統合は困難なのか 戦友会の固有性と組織間のつながり 角田燎
[補章1]戦友会研究への招待 非体験者が参加する戦友会という謎 角田燎
第2部 元兵士をめぐるまなざしの交錯
なぜ憲兵の体験や記憶は忘却されたか 未発に終わった全国憲友会連合会の「引き継ぎ」から 後藤杏
攻囲される日本郷友連盟 公文書から国家の認識に迫る 白岩伸也
未来出征軍人会 第二次世界大戦前夜におけるアメリカ在郷軍人会と大学生 望戸愛果
自衛隊体験の使い道 自衛隊退職者が書いた書籍の分析から 津田壮章
[補章2]兵士の史料への招待 捨てる/拾うの位相から 白岩伸也
第3部 残された言葉との対話
書かれたものをとおして戦争体験者とつながるには 堀川優奈
陸軍士官学校からエリートビジネスマンへ ある六十期生の「陸士経験」と戦後 塚田修一
歴史への謙虚さ 非体験者による歴史実践の可能性 清水亮
「わだつみ」という〈環礁〉への航路 ミュージアム来館者調査から 那波泰輔
エピローグ 環礁の屑拾い 「未定の遺産」化の可能性 清水亮・白岩伸也
あとがき
執筆者プロフィール/エッセイ
【編者略歴】
清水 亮(しみず・りょう)
1991年、東京都新宿区生まれ。慶應義塾大学環境情報学部専任講師。主な著作に、『「予科練」戦友会の社会学――戦争の記憶のかたち』(新曜社、2022年、日本社会学会奨励賞受賞)、『「軍都」を生きる――霞ヶ浦の生活史1919-1968』(岩波書店、2023年)、「歴史実践の越境性」(『戦争社会学研究』6 巻、2022 年)などがある。
などがある。
白岩伸也(しらいわ・しんや)
1990年、静岡県静岡市生まれ。北海道教育大学旭川校准教授。主な著作に、『海軍飛行予科練習生の研究――軍関係教育機関としての制度的位置とその戦後的問題』(風間書房、2022年)、「戦死をめぐる記憶と教育の歴史――予科練之碑設立の経緯と背景を中心に」(『教育学研究』89巻第2号、2022年、日本教育学会奨励賞)などがある。
角田燎(つのだ・りょう)
1993年、東京都東久留米市生まれ。立命館大学立命館アジア・日本研究機構専門研究員。主な著作に、『陸軍将校たちの戦後史――「陸軍の反省」から「歴史修正主義」への変容』(新曜社、2024年)、「特攻隊慰霊顕彰会の歴史――慰霊顕彰の「継承」と固有性の喪失」(『戦争社会学研究』4巻、2020年)などがある。
【ジャンル】人文書/歴史学・日本近代史・社会学・教育学

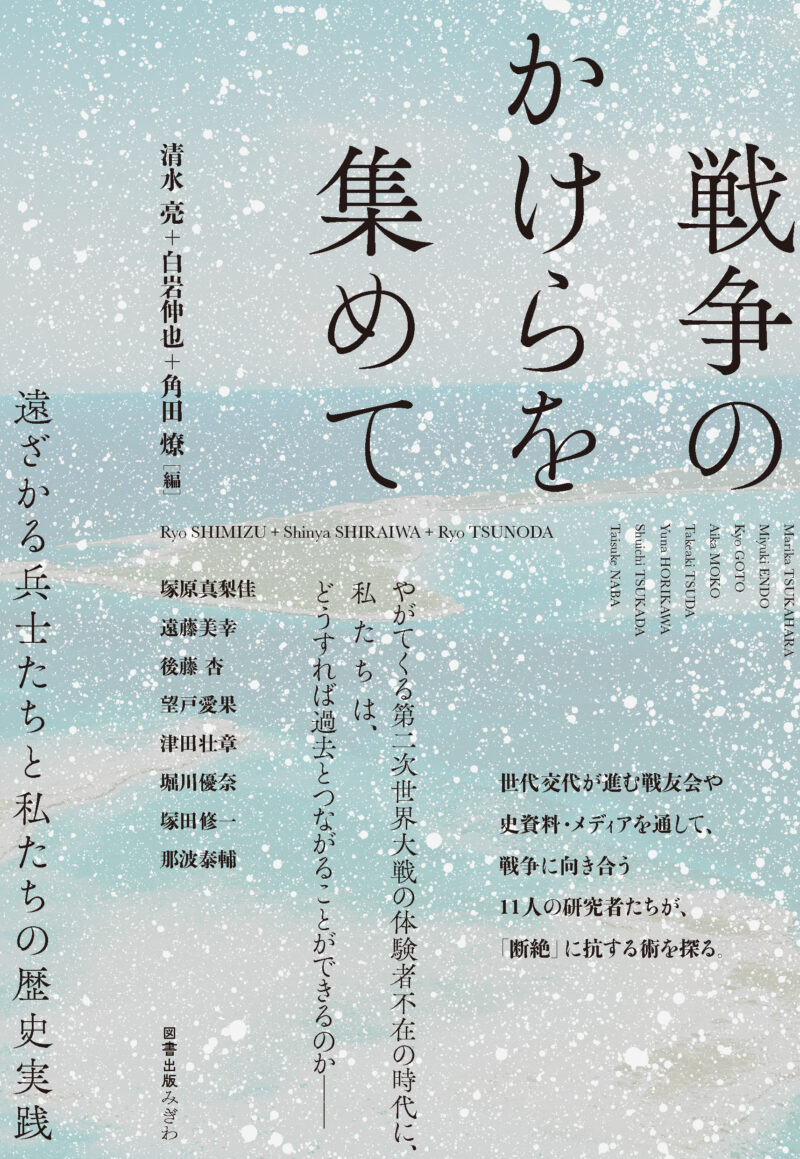
2件のコメント
コメントはできません。